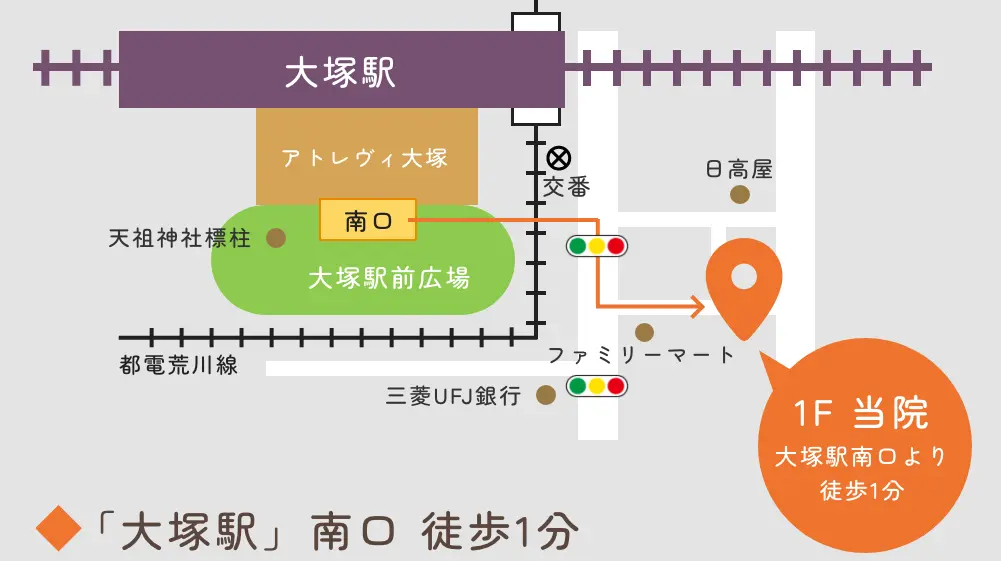睡眠外来
sleep
睡眠外来のご案内

当院の睡眠外来では、不眠症、睡眠時無呼吸症候群、睡眠時随伴症や睡眠関連運動障害をはじめとした、多様な睡眠の不調に対応しています。睡眠は心身の健康を支える重要な時間であり、質の良い眠りがとれない状態が続くと、日中の活動性の低下や気分の落ち込み、集中力の低下、生活習慣病のリスク増加につながります。
「眠れない」「寝ても疲れが取れない」「睡眠中に異常な行動をする」といった症状は、生活習慣や環境だけでなく、身体的・精神的な要因が関わっている場合もあります。当院では、問診や検査を通して原因を明らかにし、一人ひとりに合った治療や生活改善をご提案します。
このような症状はご相談ください
- 寝つきが悪い、途中で何度も目が覚める、朝早く目が覚める
- 睡眠中に大きないびきをかく、呼吸が止まっていると言われた
- 日中の強い眠気、集中力や作業効率の低下
- 夢の中の行動が現実に出てしまう、寝ぼけて歩く、寝言が激しい
- 足のむずむず感や動かしたくなる感覚で眠れない
不眠症
不眠症は、寝つきに時間がかかる(入眠困難)、途中で何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、眠っても疲れが取れない(熟眠障害)などの状態が続く病気です。夜の睡眠不足は日中の集中力低下や意欲の減退、気分の落ち込み、作業効率の低下などに繋がります。原因としては、ストレスや生活リズムの乱れ、カフェインやアルコールの摂取、環境の変化、持病による痛みやかゆみ、精神的な不安や抑うつなどが挙げられます。脳内で睡眠と覚醒を調整する仕組みや神経伝達物質(セロトニンやメラトニンなど)の働きの乱れも関係しています。症状の背景には生活習慣や環境要因が複雑に絡むため、原因を整理しながら眠りやすい状態をつくることが改善への近道です。
診断は問診を中心に行い、必要に応じて睡眠日誌や簡易検査で状態を把握します。治療は生活習慣の見直し、睡眠衛生の改善、薬物療法や認知行動療法などを組み合わせて進め、再び自然な眠りが得られる状態を目指します。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に呼吸が何度も止まり、浅い睡眠や低酸素状態が繰り返される病気です。本人は気づきにくいですが、家族から「いびきが大きい」「呼吸が止まっている」と指摘されて発見されることが多くあります。
よくみられる症状には、日中の強い眠気、集中力低下、朝の頭痛、起床時の口の渇き、夜間の頻尿などがあります。原因は、気道が睡眠中に狭くなる閉塞性タイプ(肥満、扁桃肥大、顎の形などが関与)と、脳からの呼吸指令が弱まる中枢性タイプがあります。放置すると高血圧、心疾患、脳卒中などのリスクが高まることが知られています。
治療法には、睡眠中に鼻から気道に空気を送り続けるCPAP療法(持続陽圧呼吸療法)、口腔内装置(マウスピース)による下顎の前方固定、体位療法(横向き寝の習慣化)、減量や生活習慣改善、必要に応じた外科的手術などがあります。症状や原因に合わせた治療を選択することで、睡眠の質や日中の活動性が大きく改善し、合併症の予防にもつながります。
当院でも検査からCPAP導入・管理まで行っています。
睡眠時随伴症・睡眠関連運動障害など
睡眠時随伴症や睡眠関連運動障害は、眠っている間に異常な行動や感覚が現れる状態の総称です。夢遊症(寝ぼけて歩く)、悪夢で叫ぶ、歯ぎしり、周期性四肢運動、むずむず脚症候群などが含まれます。本人や同室者の睡眠を妨げる行動や音、睡眠の質の低下、日中の眠気や集中力低下がみられることがあります。
原因は、睡眠構造や深さの乱れ、ストレス、睡眠不足、薬やアルコールの影響、神経系の病気など多様です。診断は問診や睡眠中の行動観察、必要に応じて脳波や筋電図を含む検査で行います。治療は安全面の確保を最優先に、生活リズムの調整や環境整備を行い、症状に応じて薬物療法や行動療法を取り入れることで改善を図ります。