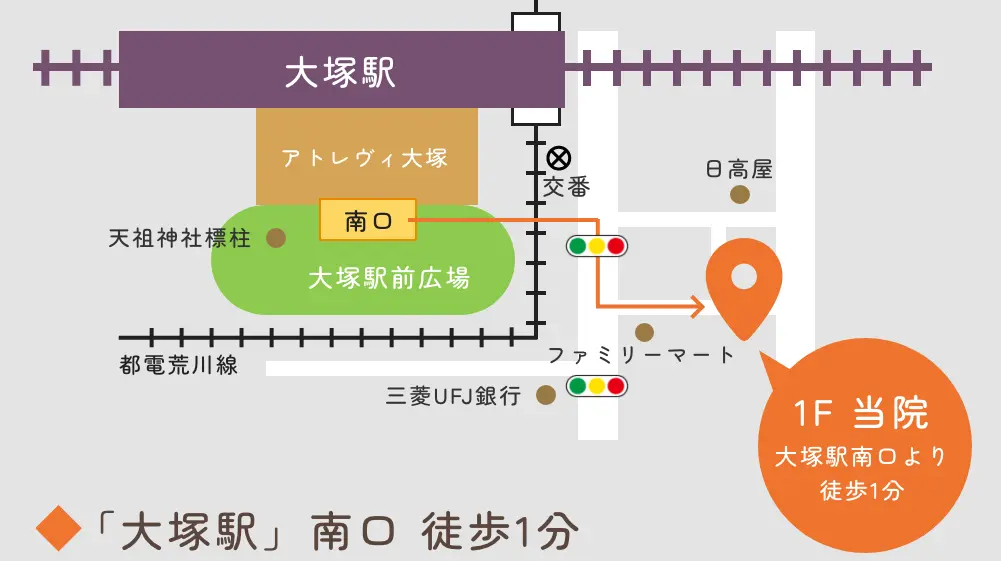心療内科・精神科
psychosomatic
うつ病
うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下が長期間続き、これまで楽しめていたことに興味が持てなくなる病気です。単なる気分の浮き沈みとは異なり、日常生活や社会生活に支障をきたす状態が数週間から数か月以上続きます。世界的にも多くの人が経験する身近な病気で、適切な治療と支援により回復が可能です。
よくみられる症状としては、憂うつ感、興味や喜びの喪失、疲れやすさ、集中力や判断力の低下、罪悪感や自己否定感、将来への悲観的な考えなどがあります。また、睡眠障害(不眠や過眠)、食欲の増減、頭痛や胃の不調など身体面にも症状が出ることがあります。症状は軽度から重度まで幅があり、人によって現れ方も異なります。
原因は一つではなく、脳内の神経伝達物質のバランス変化、遺伝的要因、過度なストレス、過労、生活環境の変化、喪失体験、持病などが複雑に関わると考えられています。早期に専門医へ相談し、原因や背景に応じた対応を行うことが、回復と再発予防につながります。
双極性障害(躁うつ病)
双極性障害は、気分が大きく高ぶる「躁状態」と、沈んでしまう「うつ状態」が周期的に現れる病気です。単なる気分の浮き沈みではなく、脳の感情や行動を調整する働きに変化が生じることで、生活に支障が出ることがあります。発症の時期や症状のパターンは人によって異なりますが、早期の理解と治療により安定した生活を送ることが可能です。
躁状態では、睡眠時間が少なくても疲れを感じない、活動的になりすぎる、話が止まらない、計画が大きくなり無理な行動をとるなどの症状がみられます。一方、うつ状態では、気分の落ち込み、意欲や集中力の低下、物事が楽しめない、自己否定感などが続きます。これらの状態が交互に、または混ざった形で現れることもあります。
原因は一つではなく、脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミンなど)のバランス変化、遺伝的な要因、強いストレス、生活リズムの乱れなどが複雑に関与します。双極性障害は正しい診断と継続的な治療により再発を予防できる病気です。「気分が極端に変わる」「調子の良すぎる時期と落ち込む時期がある」と感じたら、お気軽にご相談ください。
パニック障害
パニック障害は、突然理由もなく強い動悸、息苦しさ、めまい、胸の圧迫感などの発作が起こり、「このまま倒れるのでは」と感じる状態が繰り返される病気です。発作は数分から30分ほどで落ち着きますが、その強い恐怖から「また起こるのでは」という予期不安が生じ、外出や乗り物を避けるなど生活範囲が狭まることがあります。
身体検査では異常が見つからないことも多く、脳内で不安や恐怖を調整する神経伝達物質(ノルアドレナリン、セロトニンなど)の働きの変化が関わると考えられています。過労や生活の変化、心理的ストレスが引き金になることもあります。パニック障害は適切な治療で改善可能な病気です。
社交不安障害(SAD)
社交不安障害は、人前で話す、食事をする、初対面で挨拶をするなどの場面で過度な緊張や不安を感じ、その結果、赤面、声や手の震え、発汗、動悸などが現れる病気です。「失敗したらどうしよう」「評価されるのが怖い」という思いが先立ち、場面を避けるようになると、学業や仕事、人間関係に影響が出ることがあります。
原因としては、不安を調整する脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)の働きの変化、過去の経験や性格傾向(慎重、恥ずかしがり)、環境的要因などが複合的に関与します。性格の問題ではなく治療可能な病気です。日常の中で緊張が生活の妨げになっていると感じたら、安心してご相談ください。
全般性不安障害(GAD)
全般性不安障害は、明確な理由がなくても、仕事、家族、健康、将来など様々なことが常に気になり、不安や心配が長期間続く病気です。不安は制御が難しく、肩こり、頭痛、胃の不快感、疲れやすさ、眠りの浅さなど身体の症状を伴うこともあります。
原因は、不安を調整する脳内物質(セロトニンやGABAなど)の働きの変化、過労や環境の変化、過去の経験などが複雑に関係していると考えられます。「心配しすぎ」と自分を責める必要はありません。生活に支障が出る前に専門家に相談し、不安の正体を整理することが改善の第一歩です。
強迫性障害(OCD)
強迫性障害は、「手が汚れているのでは」「鍵を閉め忘れたのでは」などの不安な考え(強迫観念)が繰り返し浮かび、それを打ち消すために手洗いや確認行為(強迫行為)を何度も繰り返してしまう病気です。過剰だと分かっていてもやめられず、時間やエネルギーが奪われ、生活や仕事に影響が出ます。
原因には、不安や行動制御に関わる脳の回路の働きの変化、セロトニンなど神経伝達物質のバランスの乱れ、性格傾向やストレスなどが複合的に関与します。強迫性障害は適切な治療で症状を軽減できる病気です。「気になって何度も繰り返してしまう」ことで生活が制限されている場合はご相談ください。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症は、対人コミュニケーションや社会的な関わり方に特性があり、行動や興味の範囲が限られる傾向を持つ発達特性です。必ずしも知的な遅れを伴うわけではなく、強みと困りごとが共存します。
よくみられる特徴には、相手の表情や声の調子から気持ちを読み取りにくい、雑談や暗黙のルールが分かりにくい、予定や環境の変化が苦手、特定の分野に強い関心と集中力を示すなどがあります。
原因は一つではなく、脳の発達過程での情報処理の特性や遺伝的要因が関与すると考えられています。ASDは病気というより脳の特性であり、環境や周囲の理解、配慮によって生活のしやすさが大きく変わります。困りごとが続く場合は、特性に合ったサポートや環境調整の方法を一緒に探していきましょう。
注意欠如・多動症(ADHD)
注意欠如・多動症は、不注意、多動性、衝動性といった行動特性が目立つ発達障害の一つです。子どもだけでなく大人にも見られ、生涯にわたって生活や仕事に影響することがあります。
不注意の例としては、物忘れや約束の失念、作業や話に集中が続かない、ケアレスミスが多いなどがあります。多動性は落ち着いて座っていられない、手足を動かし続けるなど、衝動性は思いつくとすぐ行動してしまう、順番を待つのが苦手などです。
原因には、注意や行動制御に関わる脳の働きの特性、神経伝達物質(ドーパミンやノルアドレナリンなど)の機能差、遺伝的要因が関与します。ADHDは特性を理解し、環境を工夫することで能力を発揮できる場面が増えます。困りごとを一人で抱え込まず、特性に合った支援を活用しましょう。
適応障害
適応障害は、生活上の環境変化や強いストレスをきっかけに、気分や行動の変化が現れ、日常生活に支障が出る病気です。新しい職場や学校、転勤、引っ越し、人間関係の変化、身近な人の病気や別れなど、明確な出来事に反応して起こることが多いのが特徴です。
よくみられる症状には、気分の落ち込み、不安感、焦り、いらだち、意欲の低下などがあります。集中力が下がる、物事に興味が持てない、涙もろくなるなどの精神的変化のほか、不眠、食欲の変化、頭痛、胃の不快感など身体面にも症状が現れることがあります。時には、ストレス状況を避けようとして欠勤や遅刻が増えたり、人付き合いを避けるようになることもあります。
原因は、ストレスに対する心身の反応と環境要因が重なり、もともとの性格傾向や過去の経験が影響する場合もあります。適応障害は、ストレスの原因や環境を整理し、対処法や支援を整えることで回復が期待できる病気です。「今の状況がつらくて続けられない」と感じたら、早めにご相談ください。
身体症状症(身体表現性障害)
身体症状症は、検査で明らかな異常が見つからないにもかかわらず、痛みやしびれ、吐き気、倦怠感、呼吸のしづらさなどの身体症状が長く続き、日常生活に支障をきたす病気です。症状は気のせいではなく、実際に強く感じられるため、ご本人にとっては非常につらいものです。
よくみられる症状には、慢性的な頭痛、腹部や胸部の不快感、手足のしびれや力の入りにくさ、動悸、息苦しさなどがあります。症状が日によって変わる、時間帯によって強まることもあります。また、症状への不安や心配が続くことで、さらに体調が悪化することもあります。
原因は一つではなく、心理的ストレスや生活環境の変化、過去の体験に加え、脳が身体からの感覚信号を処理する仕組みの変化が関与すると考えられています。身体症状症は、症状そのものだけでなく、それに伴う不安や生活のしづらさにも目を向け、心身の両面から整えていくことで改善が期待できます。
睡眠障害
当院では、睡眠時無呼吸症候群、不眠症、睡眠時随伴症や睡眠関連運動障害を含めた寝ぼけ行動などの多様な睡眠障害の治療のために、睡眠外来を設けています。睡眠障害は、日中の強い眠気や集中力の低下、気分の落ち込み、生活リズムの乱れなど、心身の健康に幅広い影響を及ぼします。原因は生活習慣や環境、身体的・精神的要因などさまざまで、放置すると高血圧や心疾患、抑うつ症状などのリスクが高まることもあります。
当院の睡眠外来では、問診や必要に応じた検査を行い、原因や症状に応じた治療や生活改善のご提案をいたします。詳しい診療内容や各疾患の説明については、下記リンクより「睡眠外来」のページをご確認ください。
睡眠外来について詳しくみる認知症
認知症は、記憶力や判断力、注意力などの認知機能が徐々に低下し、日常生活に影響が出る病気の総称です。加齢による物忘れとは異なり、体験そのものを忘れる、同じ質問を繰り返す、段取りが難しくなるなどの変化がみられます。
よくみられる症状には、記憶障害のほか、時間や場所の感覚があいまいになる見当識障害、物事への興味の低下、感情の変化などがあります。これらは徐々に進行し、本人だけでなく家族にも負担がかかることがあります。
原因には、アルツハイマー型、脳血管性、レビー小体型など複数のタイプがあり、それぞれ背景や進行の仕方が異なります。進行を完全に止めることは難しい場合もありますが、早期に状態を把握することで、生活環境の調整や支援体制の整備がしやすくなります。本人の望む生活を長く続けられるよう、状況に合わせた対応が大切です。
統合失調症
統合失調症は、考えや感情のまとまりに変化が生じ、現実の受け止め方が揺らぐ病気です。発症は思春期から成人初期に多くみられますが、年齢を問わず起こる可能性があります。
よくみられる症状には、存在しない声が聞こえる幻聴、根拠のない被害的な考え、話のまとまりにくさ、感情の平板化、意欲の低下などがあります。急性期には生活や学業、仕事が続けにくくなることもありますが、落ち着いた時期には社会生活を送ることも可能です。
原因は一つではなく、脳内の神経伝達物質(特にドーパミンなど)の働きの変化、遺伝的要因、ストレスや生活環境が関与すると考えられます。症状や経過に合わせた治療と支援の組み合わせが、生活の安定に繋がります。
家族相談
家族相談は、ご本人の症状や行動にどのように対応すればよいか迷う方や、受診のきっかけづくりをしたいご家族のための窓口です。病気や特性の理解を深めることで、関わり方や声かけの仕方が変わり、家庭内の負担が軽くなることがあります。
よくあるご相談には、症状への接し方、生活や服薬のサポート方法、学校や職場との連携の仕方などがあります。また、ご家族自身の疲れやストレスが強くなる前にサポートを受けることも重要です。
原因や背景は人によって異なりますが、家族が一人で抱え込むことは、双方にとって負担が大きくなります。状況を整理し、役割分担や支援先を明確にすることで、安心して支えられる環境づくりが進めやすくなります。
森田療法
森田療法とは、主に神経症の治療に用いられる精神療法です。元々は入院によるプログラムが主流でしたが、時代の流れとともに現代では外来で森田療法を行う医療機関が増えています。当院でも適応のある患者様には森田療法のアプローチを取り入れており、薬物療法と非薬物療法を同時に行うことにより、より一層治療効果が高まると考えています。当院は森田療法の自助グループ”生活の発見会”の協力医でもあります。
Schedule
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ● | / | / | / | ■ | ▲ | ▲ |
| 15:00-19:00 | ● | ● | / | / | ● | / | / |
休診日:水曜/木曜/祝日
■ : 女性医師による診察
▲ : 土曜・日曜は10時〜15時まで診療