先日ある方から、私のコラムの中で精神医学の話は教科書的で読みづらいというお叱りを受けました。そう言われて、改めて過去の医学コラムを読みなおしてみますと、確かに一般の方には難解かなと感じました。
現在妥当であると考えられている知見をできるだけ正確に伝えようと考えると、あまり面白おかしく書くことができないのだからやむを得ないかなとも思いましたが、よく考えるとそれだけではありませんでした。拙文をさらに読み難くしている元凶は私の一人合点にあると気付いたのです。
つまり、一般の方には耳慣れない言葉を、自分では周知の事実であるとの前提で話を進めているために、医学生向けの教科書のような文になってしまったようです。こういう傾向は自分の専門分野になればなるほど顕著になりがちです。
そこでこれからはup-to-dateな話題だけではなく、医学用語の解説を時々書いてみることにしました。今回はその一回目です。これまでのコラムにも盛んに登場したレセプターというものを説明してみましょう。
レセプターあるいはリセプターは医学の世界では3つの次元で使われています。まず第1は器官(organ)のレベルです。すなわち外界や体内からの刺激を感知する器官のことをレセプターといいます。日本語では受容器とも言います。たとえば視覚情報の場合には眼球の網膜がレセプターです。
第2のレベルは細胞レベルです。刺激の受容器官の中で内外の刺激に反応する細胞がレセプターです。日本語では受容細胞とも呼びます。先ほどの視覚を例にとれば、網膜にある視細胞(錐状体、杆状体)がレセプターに当たります。
最後は分子レベルで使われるレセプターです。これは各受容細胞の構造上、刺激を感受して、それを細胞全体にシグナルとして知らせる分子およびその複合体のことをレセプターといいます。視覚の場合には視細胞に存在するロドプシンやヨドプシンという物質が光受容体です。
このようにレセプターというと厳密にはどのレベルにおけるレセプターなのかが問題となりますが、現在はただ単にレセプターと言った場合には通常、第3のレベルである細胞膜、細胞質あるいは核内にある分子構造を指します。
また、レセプターは内外すべての刺激に対応して存在しますが、現在もっとも研究が進んでいて、頻繁に話題になるのは神経伝達物質(neurotransmitter)や内分泌(hormone)などの特異的な物質(リガンド)を感知して、シグナルとして細胞の状態を変化させる化学的レセプターです。
私の専門である神経科学で問題となる、神経と神経の間のシナプスや神経と各種臓器の間のシナプスにおける化学的神経伝達物質と反応するレセプターは細胞膜を貫通するタンパク質でできていて、細胞膜の中に埋もれています。
レセプターは反応する物質が決まっています。どんな物質にも反応するレセプターというものはありません。反応する相手によってドパミンレセプター(D受容体)とかセロトニンレセプター(5TH受容体)と呼ばれます。
最近はそれぞれのグループがさらに幾つものサブタイプに分けられるようになりました。例えば、現在のところドパミン受容体はD1、D2,D3,D4,D5受容体といった5種類あることが知られています。それぞれ特異的に対応するリガンドがあります。
レセプターの最大の特徴はこの「特異性」という性質です。特定のリガンドとしか結合して反応しないのです。この特異性はそれぞれの分子構造の違いによって生まれます。周囲にどんなにいろいろな物質がたくさん存在していても、自分の形に当てはまる構造をした物質でないと、そのレセプターにとりつくことができません。
この特異性を説明するために昔から「鍵と鍵穴」が喩えられてきました。

上の図はGABA受容体に生理的に生体内に存在するGABAの他に、ベンゾディアゼピン(benzodiazepine)、バルビツール酸(barbiturate)、ピクロトキシン(picrotoxin)といった薬物が結合する様子を模式化したものです。
鍵穴にあたるレセプターは自分の形とピッタリと合致する形をした物質しか受け付けません。実際には化学区的な構造式の一部分がお互いに適合することによって結合の度合い(親和性)が決まるのです。 生体内で生理的にレセプターに結合してその細胞に作用(興奮または抑制)する神経伝達物質やホルモンなどがリガンドであるということになります。
リガンド(マスターキー)と似た構造式(鍵の特徴)を持っている物質は、本来のリガンドでなくてもレセプターに結合することができます。合鍵みたいなものです。そういう物質が薬として合成されるわけです。
この合鍵に相当する物質の中で、結合することによって細胞に本来のリガンドと同様の変化をもたらす物質をアゴニスト(作動薬)と言います。これに対して結合するだけで細胞に変化をもたらさない物質をアンタゴニスト(拮抗物質あるいは拮抗薬あるいは遮断薬)と呼びます。
椅子取りゲームをご想像ください。アンタゴニストを加えると、レセプターにとりついて鍵穴を占拠してしまうために本来のリガンドが結合する余地がなくなってしまうために、そのレセプターを介する機能が低下します。
結合といっても、レセプターとリガンド、アゴニスト、アンタゴニストとの結合は、一度くっついたら離れないのではありません。くっついては離れ、くっついては離れを繰り返しているのです(動的平衡状態)。ですからアンタゴニストを適用したとしてもリガンドの作用が全く遮断されるわけではありません。作用の確率が減少するだけです。
また、化学物質の中にはレセプターに結合して一部はアンタゴニストとして働くが、一部はアゴニストの作用も持っているというものもあって、実際にはとても複雑ですが、これ以上は専門的すぎますので省略させていただきます。
今後レセプターとかアンタゴニストとかいった言葉が出てきたならば、「鍵と鍵穴」を思い浮かべてください。神経伝達の状態がイメージしやすくなると思います。


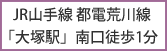


 クリニック西川
クリニック西川