脳の機能についてはまだまだ未知の部分が多く、脳の病気に対するアプローチも、現在解明されている知見だけを頼りになされているのが現状です。統合失調症の治療に関しても例外ではありません。
以前のコラムでお話ししたように、1952年にフランスの精神科医、ジャン・ドレー(Jean Delay)とピエール・ドニカー(Pierre Deniker)はローヌ・プーラン社(現在サノフィ・アベンティス社)が1950年に開発したクロルプロマジン(chlorpromazine)が統合失調症の症状を改善することを報告しました。このことがきっかけで統合失調症に対する治療の道筋が開けただけでなく、病態の解明に画期的な突破口が与えられました。
類似の構造を持つ薬物が次々に開発されて、クロルプロマジンと同じように統合失調症の精神症状を改善することが分かりました。また、1957年にはベルギーのヤンセン社のポール・ヤンセン(Paul Janssen)が開発したハロペリドール(haloperidol)が、構造式はクロルプロマジンと全く異なるにもかかわらず、クロルプロマジンに勝る抗妄想、抗幻覚作用を有する抗精神病薬であることが分かりました。
クロルプロマジンのグループ(フェノチアジン系)の薬物とハロペリドールのグループ(ブチロフェノン系)の薬物に共通した性質を研究することによって、統合失調症の本体をつきとめようとするたくさんの研究がされるようになりました。
その結果、1970年代から「ドパミン仮説」という考え方が統合失調症の病態解明の主流となりました。ドパミン仮説とは、統合失調症では中脳や辺縁系におけるドパミンの機能が亢進しているという理論です。臨床的に統合失調症の症状を改善する薬物は共通して、シナプス間におけるドパミン遮断作用(正確にはドパミンD2遮断作用)を持つことが分かったことがこの仮説の出発点です。
その後、動物実験、統合失調症の患者さんの死後脳の化学的分析および陽電子放出断層撮影(PET)による患者さんの画像診断などからも概ね正しいと考えられています。
しかし、ドパミン仮説は統合失調症の幻覚や妄想といった陽性症状についてはうまく説明できるのですが、幻覚、妄想よりもより中核的な症状ではないかと考えられる自閉(引きこもり)、感情の平板化、意欲の低下といった陰性症状についてはドパミンの過剰では説明がつきませんでした。
事実、ドパミン遮断効果を持つ抗精神病薬では陽性症状は改善するのですが、陰性症状には効果がありません。ドパミン仮説は間違いではなく、確かに統合失調症の一側面に明るい光を当てました。しかし、その光だけでは統合失調症の全容を照らし出すには不十分だったのです。
1980年にJ.S.Kim等が統合失調症患者さんの髄液中のグルタミン酸濃度が低下していることを報告して、統合失調症の発症メカニズムとしてグルタミン酸の異常を提唱しました。この報告は再現性に欠けるものでしたが、グルタミン酸神経機能にスポットライトをあてたことは功績と言えます。
その後1982年に、1952年に麻酔薬として開発されたにも関わらず、幻覚や妄想などの統合失調症とよく似た症状を引き起こす副作用があるために人への適用が中止された、フェンサイクリジンという薬物がグルタミン酸受容体を阻害することが判明しました。その後、フェンサイクリジン以外のグルタミン酸受容体阻害物質でも統合失調症様症状が惹起されることが分かりました。また、動物実験や遺伝子研究などからもグルタミン酸が統合失調発症に関与することを示唆する結果が次々と得られました。グルタミン酸神経機能の低下によって統合失調症が発症するとする「グルタミン酸仮説」が注目されるようになったのです。
グルタミン酸受容体阻害物質は幻覚や妄想といった陽性症状だけではなく、引きこもり、意欲低下・減動、感情の表出障害といった陰性症状をも引き起こします。グルタミン酸仮説は従来のドパミン仮説では説明のつかない部分をカヴァーできるのです。グルタミン酸仮説が脚光を浴びるようになったのはこの理由からです。
それでは、今まで信じられてきたドパミン仮説は嘘だったのでしょうか。そうではありません。神経伝達機構は相互に密接な関係を持っています。グルタミン酸受容体、その中のNMDA受容体を阻害すると、ドパミン作動性神経機能の亢進をもたらします。結果として、幻覚や妄想を生み出す。ドパミン仮説自体は決して間違いではないのです。ただ、そのドパミンの過剰状態をグルタミン酸系の異常が引き起こす可能性が分かってきたということです。
長らくドパミン仮説で説明がつかなかった統合失調症の陰性症状の治療に一筋の明かりをともしたグルタミン仮説ですが、これで統合失調症のすべてが解決するかというと、そう宣言することができないのが現状です。
グルタミン酸仮説に基づいて、グルタミン酸受容体に作用する治療薬開発が進められていますが、グルタミン酸系の薬物は従来のドパミン系薬物に比べてはるかに弱い臨床的治療効果しか得られません。今のところ、ドパミン系薬物による治療における補助治療薬あるいは効果増強薬としての地位に留まっています。
一方、統合失調症においてもセロトニンの機能障害が関与していることを示す実験結果が得られて、セロトニン受容体拮抗物質が統合失調症の治療薬として開発されています。
この他にも、統合失調症の発症にはニコチン受容体やセクレチンなどの関与も考えられており、そういった受容体へ作用する物質を治療薬として開発する努力も着々と進んでおります。
私は今後さらに多くの神経伝達物質の統合失調症発症への関与が明らかになってくると想像しています。統合失調症の複雑な精神症状が単一の神経伝達物質の機能異常だけに起因するとは考えられないからです。また、現在のところは統合失調症という病名で十把一絡げにしていますが、統合失調症の患者さんの症状や経過は実際には千差万別であり、いろいろなサブタイプがある症候群であると思います。したがって、ある患者さんにはドパミン系の関与が強く、別のある人の場合にはセロトニン系やグルタミン酸系の関与の度合いが大きいという違いがあって当然だと思います。
私はこれからの近い将来に、統合失調症に関連した物資がさらに数多く発見されるだろうと予想しております。そしてその後、出そろった役者が整理統合されて、そういった様々な変化を引き起こす為の、シンプルな共通原理がつきとめられていくと想像しています。
統合失調症という難敵攻略作戦において、現在はまだその一里塚にあるのだと思います。最終目標までの道のりはまだまだ遠いと思われますが、着実な一里であることは確かです。はしゃがず、あきらめずに統合失調症に挑み続けていきたいものです。
ところで、グルタミン酸は必須アミノ酸の一つで、神経伝達物質よりは「旨味」の成分としてのほうが有名です。旨味調味料である「味の素」の主成分はグルタミン酸ナトリウムとイノシン酸ナトリウムです。
グルタミン酸が脳内で重要な働きをしていることが分かった当時、「味の素を食べると頭が良くなる」という都市伝説が生まれて、我が子に大量の味の素を食べさせる母親が出現しました。
実際には経口的に取り入れられたグルタミン酸は体内で直ちに代謝されて各種タンパク質の合成に使われます。直接脳内に移行することはありません。したがって、いくらたくさん味の素を食べても頭は良くなりませんし、統合失調症も治りません。それどころか大量に摂取すると血管拡張作用が発現して頭痛で苦しむことになります。
細胞レベルの出来事と経口的に取り入れる物質の多寡とは同次元では論ずることができません。この医学的な常識を一般の方が理解していないのをよいことにして、訳の分からないサプリメントが出回っています。くれぐれもご用心ください。


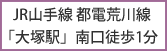


 クリニック西川
クリニック西川