成年後見制度については以前のコラムでも取り上げましたが、これまでに私が関わった事例を通して感じた幾つかの問題点を中心に、再度考えてみたいと思います。
この制度は民法第1編第2章第2節の「行為能力に関する規定」で定められています。平成12年以前の後見制度では本人の判断能力に応じて、禁治産と準禁治産の2つの類型に分けられていました。禁治産は心神喪失の者、準禁治産は心神耗弱者を対象としてそれぞれについて保護の内容を規定していました。しかし、この制度では判断能力が低下の程度が心神耗弱ほどではないが、一定の支援がなければ自己の安全や適切な財産管理をすることができない人を保護することができませんでした。
国は、この欠点を補うこと、またその人の状況に応じて弾力的で利用しやすい後見制度を国民に提供することを目指して民法の改正を図りました。この改正案は平成11年7月6日(第145回国会)の本会議において承認されて、平成12年4月1日から新しい成年後見制度が施行されたのです。
旧法における禁治産および準禁治産の法定後見は判断能力の低い順に「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に改められました。またこの3つの法定後見以外に、平成11年12月3日の第146国会で新設された「任意後見契約に関する法律」に基づいて「任意後見」という制度を設けました。
「後見」は従来の禁治産に、「保佐」は準禁治産に相当します。「補助」は新たに設けられた類型で、判断能力が不充分ではあるものの、保佐の対象になる程度には至っていない人を対象としています。
「後見」が認められ、成年後見人が選任されて後見が開始されますと、本人の行為の全般について成年後見人が代理することができますし、本人がした行為を取り消すことができます。
「保佐」の場合には判断能力がまったくないというわけではないので、日常的な行為は本人に任せますが、財産に関する重要な行為には選任された保佐人の同意が必要になります。保佐人の同意を得ないで行った重要な財産行為は取り消すことができます。また、家庭裁判所は必要に応じて保佐人に代理権を与えることができます。
新しく設けられた類型の「補助」の対象者は自己の安全保持や財産の管理・処分もでき得るが、その判断が充分とはいえないために、誰かに代わってやってもらったほうが危険性が少ないという程度の人です。ですから、選任された補助人は本人を代理する権限や、本人が行う重要な行為に関して同意する権限が与えられますが、その代理権や同意権の範囲や内容は家庭裁判所が個々に判断して決定します。そして代理権や同意権が与えられた事項については、補助人は成年後見人や保佐人と同様の権限を持ちます。
しかし、「補助」が「後見」や「保佐」と大きく異なる点は、補助を開始するためには本人の申し立てあるいは同意が不可欠であるということです。補助の対象者は一定水準の判断能力を有しているわけですから、補助という支援を受けるか否かについては自己決定するべきであるという考えです。
新しく立法された任意後見制度は、将来、精神障害によって判断能力が低下した場合に備えて、本人が予め任意後見人になってもらう人とその権限についての契約を任意後見受任者と結ぶという制度です。この契約を結んでおけば、現在は自立した生活を送っていられても、いざ本人の判断能力が法定後見の補助以上に障害された場合に、家庭裁判所が任意後見人をさらに監督する任意後見監督人を選任して、任意後見受任者が任意後見人となって、契約が実効化されます。
この制度は契約締結時には判断能力に問題がない人を対象としていますので、任意という名前の通り、本人の申し立てまたは同意がなければならないことは言うまでもありません。
この制度が実施されてから8年になりますが、高齢化に伴う認知症の増加と、関係者の啓蒙活動の結果、年々10~30%位の割合で利用者が増えています。平成18年度は自立支援法の改正にともなって、施設入所者に対する後見申立が集団で行われたために前年比50%を超える増加率でした。この年が異常に多かったために(全申立件数:32,629件)、平成19年度は計算上では前年比23%の減少(全申立件数:24,988件)となりましたが、成年後見制度の利用者は今後も増加していくものと思われます。
類型別に見ますと「後見」が圧倒的に多く、平成19年度は全申立件数の85%が後見開始の審判でした。次いで、保佐、補助の順番になります。その仕組みが充分に知られていないためでしょうか、任意後見制度の利用はまだまだ多くありません。平成19年度の任意後見人監督選任の審判の申立は426件に過ぎませんでした。
審判の結果、申立の90%が認められています。取り下げや本人が死亡したことなどが9.4%あり、却下は0.3%にとどまります。
申立は本人、配偶者、四親等内の親族、身寄りのない場合には市区村長のほか検察官もすることができますが、実績としては本人の子供が最も多く、次いで兄弟姉妹、配偶者と並びます。市区村長は年々増加してきて平成19年度は6.1%でした。身寄りのいない高齢者が増えてきていることを反映しています。
成年後見制度の審判に際しては本人の精神状態を知るための資料として医師その他適当な者に鑑定をさせなければならないとされています。事理判断能力を中心とした精神の状態を鑑定するのですから、精神科医が鑑定するのが適当であると思われますが、年々増加する需要に対して精神科医だけでは迅速に対応することが困難です。
このために、最高裁判所は、精神科以外の一般科の医師でも鑑定書を書くことができるように、典型的な具体例を添えたガイドラインを作成しました。さらに、一般医がもっと容易に鑑定書を書くことができるようにと、誰が見ても一目で「後見」相当と分かるような精神障害の程度の重い事例においては特記するべきことがない場合には「特記事項なし」にチェックすれば済む、要点式の書式も作成しました。
しかし、私がこれまでに依頼された鑑定の多くは要点式のチェック方式の鑑定書で済まされるような事例はごくわずかでした。多くの事例はガイドラインに倣って書けば済むというもではなく、難しい判断を要求されるものでした。その中のいくつかをご紹介します。
1.認知症の程度はごく軽度だが、元来の性格異常が脳の老化によってカリカチュアかされて、家族や近隣住民とトラブルをくり返すようになりました。また、高額な宝飾品を次々と買い込んでしまい、莫大な借金を作ってしまった女性です。この女性は子供に恵まれなかったために、親族に当たる男性を養子にして、養子一家と同居していました。申立人はこの養子です。それまではなんとかうまくやっていたのですが、加齢とともに先程述べたような症状のほかに、養子夫婦に財産を狙われているという被害的な訴えをするようになりました。実際にこの女性は土地、家屋のほかにかなりの資産を有していました。日常生活の状態については申立人である養子夫婦からの聴取がかなりの部分を占めます。このために、本人の訴えを妄想と片付けてよいのか、申立人からの聴取内容がどれだけ客観的なものなのかを慎重に判断しなければなりませんでした。結局6回ほど往診による診察を重ねて鑑定書を書き、補佐開始の決定を受けました。
2.兄弟間で母親の処遇と財産の管理をめぐって争いがあり、その争いに成年後見制度が悪用された事例です。この女性には娘2名と息子1名の子供がいましたが、息子が知り合いの医師に後見申立のための診断書記載を頼み込みました。その医師は本人を充分に診察もしないで「自己の財産を管理・処分することができない」という診断書を書いてしまいました。息子はこの診断書を根拠に自分を後見人として後見開始の審判を申し立てるとともに、本人を「部屋の補修をする間だけ仮住まいしていてくれ」と言いくるめて、有料老人ホームへ入所させてしまいました。この入所にかかわる費用は母親の預貯金から支払っていました。これを知った娘たちはびっくり。また、何ヶ月過ぎても家に帰れないことを不審に思った本人もホームに対して退所を要求しましたが、老人ホームは「契約者は息子さんだから息子さんの要求がなければ身柄は渡せない」の一点張り。老人ホームは1年たたないと保証金を返還しなければならないので、なんとかそれまで身柄を預かっておきたかったようです。困り果てた娘たちが弁護士に相談。この弁護士から依頼を受けた私は、精神科医であることを隠して老人ホームへ往診に出向きました。簡易知能検査であるHDS-R、MMSEともに20点台の後半の得点で、記憶力や見当識に若干の機能低下があるものの重大な判断能力低下は認められませんでした。また、本人は明確に自宅での生活を希望しました。この診察結果をもとに書いた私の意見書を根拠に弁護士が強引に本人の身柄を解放しました。その後、警察の介入やらなにやら大騒動があったのですが、結局は息子の申立は取り消され、本人と娘たちがあらためて申立をして、娘と第3者の弁護士を補助人とした補助開始の審判が下りました。
3. 認知症の父と同居する一人娘から申し立てられた補佐開始の審判に対する鑑定の事例。立ち居振る舞いはしっかりしていて、食事、排泄、入浴などの日常的な行為は概ね自分でできています。補助診断として施行したMRIでもほぼ年齢相応の萎縮しか認められませんでした。しかし、外にでることがなく、買い物も自分ではできません。HDS-Rでは8点で高度認知症の範囲になります。なぜ、知能テストでこれほど低い得点になってしまうのだろうかと考えると、目の前に与えられた課題に取り組もうという意欲がないか、集中が保てないことが原因であろうと思われました。しかし、経過や面接時の観察からは治療によって回復するうつ病だとも言えません。やはり脳の機能低下が特に意欲や注意力に現れている結果であろうと判断しました。理由はともあれ、最高裁判所のガイドラインでもっとも重視されている金銭管理はまったくできない(しようとしない?)のですから、ガイドラインに従えば、保佐ではなく後見に相当します。私自身「後見とも言えるし、保佐とも言えるな」との思いを抱いたまま保佐相当という主旨の鑑定書を提出しました。案の定、後日家庭裁判所から連絡があり、裁判所でも申立の通り保佐開始の審判にするか、後見に切り替えるか判断に困っているというのです。この事例では身寄りは同居して一生懸命介護している申立人の一人娘しかいませんから、財産をめぐる争いが発生する危険性が少ないので、後見でも保佐でも事実上大きな違いは出てこないと思われますが、複雑な家族関係であった場合には難しい判断を迫られることも多いのではないでしょうか。
認知症と一口に言っても、症状の進行は教科書通りではありません。個々の症例によって機能によって障害の程度が異なります。認知症はのっぺらぼうではなく、それぞれ独特の顔をもっているのです。本当の末期になれば医師でなくても鑑定できるでしょうが、初期から進行期では注意深い観察と鑑別が必要となります。要点式の書式ではすまないのです。
また、事例1.のように認知症だけが問題ではない例も少なくありません。若い頃から何らかの精神障害にかかっていたが未治療で、認知症も加わってきたために処遇が困難になっているとしか考えられないケースにもよくお目にかかります。
この制度が一般の方にもっと理解されてくると、後見に至る前の保佐や補助の段階での申立が増えてくると考えられます。そうなると、やはり精神科医の出番が増えてきそうです。
新設された任意後見制度はまだ普及していませんが、とてもよい制度です。自分がまだしっかりとした判断能力がある段階で、将来に備えてしかるべき人と契約を結ぶことと遺言状を書いておくことは、これからの高齢者に必要なことだと考えます。


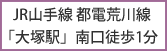


 クリニック西川
クリニック西川