平成16年5月28日に公布された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)」に基づいて裁判員制度が平成21年5月までにスタートします。
「国民の司法参加」と言われているように、裁判が身近で分かりやすいものになり、司法に対する国民の信頼が向上するものと期待されています。また、本制度の導入をにらんで平成17年11月の改正刑事訴訟法で取り入れられた公判前整理手続を活用することによって裁判の迅速化が図られています。
後期高齢者医療制度に関しては実施前の説明がまったくなされていないために大混乱をきたしました。しかし、この裁判員制度に関してはだいぶ以前から国民に向けてさまざまな啓蒙活動が行われてきました。しかしその多くは、この制度の導入の是非を問うことではなく、制度導入は既に決定事項であり、その内容を周知するためのものであったように思います。
ここで改めて裁判員制度のあらましとその問題点について列挙してみたいと思います。
まず述べておかなければならないことは、今後は裁判員として刑事裁判に参加することが原則として日本国籍を持つ成人の新たな義務となるということです。
裁判員の選出方法は各年度ごとに市町村の選挙管理委員会が、衆議院議員の公職選挙人名簿登録者から「くじ」で翌年度の裁判員候補予定者を選定して、「裁判員候補予定者名簿」として各地方裁判所に送付します。
地方裁判所はこの名簿を基に、毎年度、「裁判員候補者名簿」を作成して、その名簿に記載された人へ、その旨を通知します。その際、調査票を送付して就職禁止事由に該当しないか、1年を通じて辞退事由があるかどうか、特定の月に参加することが困難な場合はその月とその理由について調査します。この資料を基に各事件に対する候補者選びの際の参考にします。
そして各事件ごとに呼び出す候補者を、再び「くじ」で選定します。選定された候補者に対しては「質問票」と「呼出状」が送付されます。この通知を受けた人は質問票に回答して裁判所に返送しなければなりません。この質問票では欠落事由、就職禁止事由、事件に関連する不適格事由、辞退事由のあるなしについて質問がなされます。
欠落事由とは義務教育を終了していない者や禁錮以上の刑に処せられた者などです。就職禁止事由とは一定の公務員、法曹など法律関係者、警察官などです。事件に関連する不適格事由とは被告人・被害者の関係者、事件関与者などです。辞退事由とは70歳以上、学生、重要な用務があること、直近の裁判員従事などです。
質問票の回答によって明らかな欠落事由、就職禁止事由、事件に関連する不適格事由があるか、辞退事由が明らかに認められる人以外は呼び出しが取り消されることはありません。
こうなると次は裁判所に呼び出されます。裁判所は非公開で出頭した候補者の中から裁判員と補充裁判員を選任します。質問票に虚偽の記載をした場合には50万円以下の罰金または30万円以下の過料が課せられます。また、呼び出しにもかかわらず、正当な理由なく出頭しないものには10万円以下の過料が課せられることがあります。
裁判長、陪席の裁判官、検察官、被告人または弁護人は出頭した候補者に必要な質問をしてこの回答に基いて選任しないものを決定します。こういった一連の手続きをした上で、裁判所は裁判員と補充裁判員を選任・決定します。
裁判員裁判の対象事件は重大事件に限定されます。具体的には強盗致傷、殺人、現住建造物等放火、強姦致死傷、傷害致死、強制わいせつ致死傷、強盗強姦、強盗致死、覚せい剤取締法違反、危険運転致死などで、平成18年度を例にとって見ると地方裁判所で扱った事件数のおよそ2.9%(3,111件)です。
人数は、原則1つの裁判で裁判官3名、裁判員6名です。場合によっては裁判官1名、裁判員4名のこともあります。こうやって計算すると1年の間に裁判員候補者になる確率は330~660人に1人。実際に裁判員または補充裁判員になる確率は4,000人に1人ということになるそうです。
裁判員の選任手続が終わったら公判に入り、裁判員は裁判官とともに証拠書類・証拠物の検討や、証人尋問、検証、被告人質問などの証拠調べを経て、評議・評決の上、判決に関与します。この際、アメリカの陪審員制度と異なって、有罪、無罪の確定だけではなく、その量刑の決定にまで関与します。
我が国の司法に関する大きな変革であり、国民の国家に対する新たな義務が追加される大きな出来事であるにもかかわらず、制度の導入の是非に関する議論は国民の間ではほとんどなされてきませんでした。新制度ありきを前提に、啓蒙活動が進められてきたからだと思います。
今さらながら、この裁判員制度を検討してみますと、実にさまざまな問題点を抱えています。以下にその諸課題を述べてみます。
1. 参加の強制:やりたくない人までも強制的に参加させることが「意に反する苦役」を課すものとして憲法18条に違反するのではないかという意見があります。意識調査においても「参加したい」(25.6%)、 「参加したくない」(70.0%)と、圧倒的に裁判員になることを望んでいない人のほうが多いのが実情です。また、制度のあり方や事務手続きの進め方、免除事由など多くの点から、戦前の徴兵制度との類似性を指摘されています。
2. 裁判員の匿名性・安全性の確保:裁判員の氏名は被告人や他の裁判員開示されることはないというものの、世間には非合法の情報ルートがあることが現実ですから、法律で禁じられているだけでは絶対に安心とはいえません。また、氏名は知られなくても、顔は見られるわけですから、ある程度社会に顔を露出している人物、例えばタレントなどの参加の場合には匿名性は担保されません。週刊誌の、あるコラムに、「お礼参りが怖いから、裁判員になったら絶対に死刑にしてしまうか、無罪にしてしまおう」という皮肉なコメントが載っていました。あながち冗談では済まされない問題です。
3. 裁判員の秘密保持義務:裁判員は「評議の秘密」と「その他職務上知り得た秘密」について、終生の秘密保持義務を負います。違反した場合には刑事罰が処せられます。たんに「くじ」で選ばれた国民が刑事罰の威嚇の下に「墓場まで持っていく秘密」を背負わされることは過剰な義務であるとの批判があります。また、公判で行われた質疑は公開ですから、そのことについては守秘義務が生じませんが、一般人にはどれが公開でどれが非公開かの判別は困難ではないかと思われます。
4. 裁判員の資質の問題:やる気のない裁判員をどう対処すればよいかも議論されています。海外の同じような制度でも飲酒して裁判に参加したり、審理中に居眠りをするといった事例が問題にされています。そこまでいけば裁判長が解任手続きをすると考えられますが、内心の「やる気」までは判定できません。また、罰則があるとはいえ、買収によって結託して判決が操作される危険性は除去できません。
5. 裁判員の構成の問題:意識調査で分かるとおりに、裁判員に参加したい人
よりも参加したくない人のほうが圧倒的に多いのが実情です。あの手この手で裁判員逃れをする人が出てくることが予想されます。例えば過料(罰金)を払えば呼び出しに応じなくてもすむわけですから、お金を払って裁判員になることを回避する人が現れることは容易に予想されます。
ヨーロッパでは実際に、多忙な社会人は罰金を払って参加を拒否しています。結果として、裁判員は専業主婦と年金生活者が多数を占めるという傾向になります。専業主婦と年金生活者に片寄った裁判員では本来の目的である「一般市民の感覚」を代表できるのかということが問題になります。
6. 休暇および不利益の問題:「労働者が裁判員の職務を行うために休暇をとったことを理由として会社は不利益な扱いをしてはいけない。」と定めてあります。しかし、その休暇および給与の実際の運用については各企業の判断に任せられています。実際に大企業では裁判員制度専用の有給休暇制度の導入も検討されているようですが、従業員の少ない零細企業などでは裁判員で人手をとられてしまうと会社の活動そのものに支障が出てくるところもあります。裁判員の職務のために会社を休んだ場合に、解雇や昇進を遅らされたとしても、その救済は困難なのが現実です。
7. メディアによる判決操作の問題:一般の人は情報操作に対する抵抗力がない上に、感情的になりがちです。したがって今まで以上に裁判におけるメディアの影響力が大きくなる可能性が心配されます。裁判員を完全にメディアから隔離することはできません。
我が国では多数のメディアが一体となって特定の人物を吊るし上げたり、興味本位や感情的な報道に終始することは珍しくありません。1994年の松本サリン事件が代表的な例ですが、つい最近起こった四国の祖母と孫2名が殺害された事件でも危うく無実の人が犯人であるかのようにメディアによって世論操作されるところでした。
一般人の感覚を裁判に取り入れるのが目的だからといって、判決に公正さが失われてしまうことだけは断じてあってはいけないことだと思います。
8. 適用範囲の問題:一般庶民の感覚を取り入れるのが目的ならば、身近な民事事件こそが適当であると思うのですが、本裁判員制度は重大な刑事事件に限定されています。この背景にはアメリカの陪審員制度化においては、アメリカ企業が外国企業と民事事件を争う裁判において陪審員が自国アメリカの企業に有利な判決をくだすことが多いのです。もし日本の裁判員制度で民事事件にまで裁判員制度を採用すると、日本でアメリカの企業が逆の目にあうことが予想されるために、アメリカから刑事事件に限るようにとの要請があったためと言われています。
また、従来から裁判官が雇用者寄りの判決を出しやすいことから、民間感覚を取り入れることを長年要求されてきた労働裁判への裁判員の導入も見送られました。この背景にも経済界(雇用主側)からの根強い反対があったからだといわれています。
私がもっとも裁判員制度が採り入れられるべきだと考えるのは、国民が国家の責任によって被った損害を裁く国家賠償法裁判です。公害による被害、薬害による被害や冤罪による誤認逮捕被害などを被った際に、国民が国家に対して損賠賠償を求めて起こす裁判です。いくら三権分立とは言うものの、現在の仕組みでは国が被告である国を裁くために、国側の完全勝訴率が90%以上です。この国家賠償法裁判ほど国民的な一般感覚を必要としているのではないでしょうか。ところがこの国家賠償法裁判も裁判員制度の対象からははずされています。
結果として、裁判員はもっとも心的負担の大きい重大な刑事事件の裁判にだけ参加させられることになってしまいました。この裁判員制度の適用範囲はとても重大な問題であるのに、ほとんど議論されないままに決定されたように思われます。もし本当に外国や経済界からの圧力によって決められたのだとしたら由々しき問題でしょう。
9. 公判前整理手続の是非:刑事事件で公判前に争点を絞り込む手続のことです。裁判の迅速化を図るために裁判員制度の対象となる刑事裁判は全てこの手続きがなされます。裁判は迅速化されますが、手続き後に被告に有利な証拠や証人が出ても採用が制限されてしまいます。
この問題は実際には裁判員制度導入による問題ではなく、現行の政治訴訟法の問題点です。強制捜査権やその結果得られた証拠などの管理権が裁判上は一方の当事者でしかない検察官に委ねられているからです。日弁連は以前から検察官が所有する証拠の事前、全面開示を要求しています。
10. 最後に精神科医の立場からの心配と予想を述べます。心配なことは以上のように裁判員に選任された国民は多大なストレスを受けます。日常の仕事を休んで、人が人を裁くというきわめて過酷な責務を負わされます。こういう体験から精神的な病が発症することは充分に予想されます。その場合、その精神障害の治療に対して国はどのように責任を果たすのでしょうか。この点についても明快な保障はされていません。
精神科医として関心がある点は最高裁が公判の迅速化のために、公判後の精神鑑定は原則として行わずに公判前鑑定1回だけにするという方針を打ち出したことです。つまり、検察が起訴するか否かを判断する前に行う起訴前鑑定か、起訴と公判開始の間の公判前整理手続中に行われる公判前鑑定かどちらか1回しか行わないことになるようなのです。公判が始まった後では精神鑑定を請求できないことになりますから、念のために公判前鑑定をしておこうと考えて、鑑定の依頼が増える可能性が高いと思います。公判後の鑑定は多くの時間と労力を要するために、とても開業医が引き受けられるものではありませんが、起訴前簡易鑑定は充分な資料さえあれば数回の診察で判定可能です。したがって、件数が多くなると一般の精神科医にも依頼が来るかもしれません。しかし、我が国では司法精神医学に関する教育に力を注いでこなかったために、一般の精神科医では鑑定の質が保証できません。裁判員制度導入は私たち精神科医が早急に司法精神医学を研鑽しなおす必要を迫っているといえます。
以上、実施までに1年を切った裁判員制度の概要と、思いつく問題点について書いてみました。よく考えてみると、さまざまな問題点を内包して、必ずしも国民に歓迎されているとはいえない制度であることが分かります。
本制度の導入が、またもやアメリカからの要望の結果であるとの噂を耳にすると、ますますもってうんざりしてしまいます。
ところで、私のように一人で診療している開業医は辞退できるのでしょうか。おそらくは正当な辞退理由にはならないものと思われます。私自身は司法に関心がないわけではありませんが、患者さんを放り出して数日間臨時休診とすることには正直、ためらいがありますし、人を裁くことへの強い抵抗があります。できるならば、裁判員としてでなく、公判前精神鑑定業務でこの制度に参加したいと思っています。


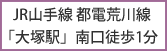


 クリニック西川
クリニック西川