従来、「痴呆」と呼ばれていた一群の病気が最近「認知症」と名前を変えました。こうした用語の変更はしばしば行われます。もう少し前には「精神分裂病」が「統合失調症」に変わりました。
ことばは使用されているうちにだんだんと堕落していき、差別的なニュアンスを帯びてくるようです。昔は貴い人をさして使われた「貴様」が現在ではかなり格下げになってしまい、むしろ侮蔑的な人称名詞になってしまっていることなどがよい例でしょう。これが病名を変更する理由のひとつです。
「統合失調症」という名称はこの病気の本質をよく表しているので、よい名称変更だと思います。しかし、「痴呆」の「認知症」への変更はよいとは思えません。なぜならば、この病態は認知機能だけがやられるわけではなく、知的機能全般が低下し、さらには感情や意欲の低下など脳の全般的な機能も低下するからです。「認知症」ではこの病気が認知機能だけが障害されるかのような誤解を与えるので、私は今まで通りの「痴呆」のほうがこの病気を正しく表しているように思います。
さて私が医学生であった当時、65歳以上の老年期におこる痴呆は一括して老年期痴呆と呼ばれていました。その脳の萎縮は加齢にともなう生理的な脳の萎縮とは量的にも質的にも違いがあり、精神症状も生理的な老衰とは質的に違う病的な症状が多く認められるにもかかわらず、正常な老化との間に明確な境界線を引くことはできないとされてきました。
これに対して、主として初老期(45歳〜65歳)に発症して特徴的な症状を示す脳の萎縮性精神病を総じて初老期痴呆と呼んでいました。当時は3つの病気が初老期痴呆と呼ばれていました。ピック病(Pick’s Disease)、アルツハイマー病(Alzheimer’s Disease)、クロイツフェルド・ヤコブ病(Creutzfeld-Jakob’s Disease)の3大初老期痴呆です。すべて原因不明の脳の変性疾患とされていたのです。
このうち、ピック病とアルツハイマー病は今でも原因不明の、脳変性疾患ですが、クロイツフェルド・ヤコブ病に関してはその後、驚くべき展開をみせることになりました。今回はこのクロイツフェルド・ヤコブ病についてお話をしたいと思います。
この病気は1920年にクロイツフェルド、1921年にヤコブと相次いで2人のドイツ人医学者によって報告されました。初めのうちは興味の消失、注意障害、記憶障害とともに歩行障害や言語障害が表れます。やがて、精神運動興奮、幻覚、妄想、意識障害、錯乱が加わって、手足の振るえや、奇妙な不随意運動、四肢の麻痺などの運動機能障害を示します。末期になると高度の痴呆に加えて筋固縮、運動麻痺、痙攣発作が見られるようになって、他の初老期痴呆よりも急速な進行を辿って一年前後で死に至りました。
亡くなった方の脳を調べると大脳皮質と皮質下の核が変性萎縮するとともに神経細胞の硬化も見られました。また、マクログリアという細胞の増殖と脳がスカスカに海綿(スポンジ)のような状態が見られました。一方、アルツハイマー病や老年期痴呆の脳に見られるような老人性の変化はまったく認められませんでした。
非常に特徴的な病気で致死率100%という重大な病気ですが、100万人に1人と稀にしか見られない病気だったので、その後あまり注目されることがありませんでした。
1950年代ニューギニアのある部族の間に、主として女性を中心にクールー病という不可思議な病気が流行していることが分かりました。クールーとは現地用語で「震える」という意味であり、運動失調や震えなどの神経症状を示して急速に痴呆化して死に至りました。致死率100%です。
研究者達はウィルス性の脳炎を疑って研究しましたが、血清の中にはウィルスの存在を示す抗体が見つからないで、原因は不明のままでした。ただ、亡くなった方の脳はスカスカにスポンジのようになっていて、症状もクロイツフェルド・ヤコブ病と酷似していました。また、古くから動物の世界で見られていたスクレイピー病の脳の病理所見ともそっくりでした。
羊がかかる奇妙な病気、スクレイピー病は18世紀の初め頃から知られていた病気です。羊がこの病気にかかると行動が落ち着かなくなり、興奮したり、疾走したりするようになる。次いで体毛が抜け落ちるほど激しく身体を木の幹や柵にこすりつける。やがて動きが鈍くなって群れを離れて、よろよろと歩き、やがて歩行困難となり、餌も食べられなくなって衰弱死します。
この羊の病気は一度かかると治ることはない。すなわち致死率100%の病気で、何の前駆症状もなく突然発症する。一頭がこの病気にかかると、しばしば同じ群れに広がり、ばたばたと死んでいく。やがて流行が収まっても、人々が忘れた頃にまたどこかに出現する謎の病気でした。死んだ羊の脳を顕微鏡で見るとスポンジ状の空胞とグリア細胞の増殖が見られました。
1930年代の後半にフランスの獣医学者がスクレイピー病にかかった羊の脳をすりつぶした物を健康な羊の眼球内に注射して忍耐強く観察をしました。あきらめかけていた頃、つまり注射後1年4ヶ月〜2年で注射された羊がスクレイピー病を発症したのです。つまり、スクレイピー病は感染症であることが証明されたのでした。
ただ、通常の感染症に比べて潜伏期が異常に長く、電子顕微鏡や免疫学的な研究を進めても原因となっているであろう菌もウィルスも見つからなかったのです。さらに驚くべきことには通常どんな細菌やウィルスも殺してしまうはずのホルマリンで処理してもスクレイピー病の病原体は死滅しないことが分かりました。また、その後の研究でこの病原体は通常の加熱処理や放射線照射でも死滅しないことも分かりました。しかも、免疫学的に抗体が作られないのです。
煮ても焼いても、消毒剤を使っても殺すことができない正体不明の病原体の存在は一部研究者の間に驚異と恐怖をもたらしました。後に映画化された小説「アンドロメダ病原体」のモデルにもなりました。
さて人のクールー病の話に戻りましょう。クールー病について研究していたカールトン・ガイジュセック(後にノーベル賞受賞)はスクレイピーについて研究していた獣医学者ウィリアム・ハドローからスクレイピー病とクールー病が酷似していることを指摘されて、クールー病患者の脳をすりつぶした物をチンパンジーへ接種して18ヶ月〜22ヶ月でチンパンジーにクールー病とそっくりの病気をひきおこさせました。さらに、このチンパンジーの脳を使って、さらに他のチンパンジーにクールー病と似た病気を伝達させました。
さらに、ガイジュセックはクロイツフェルド・ヤコブ病の患者さんの脳から採取したサンプルをチンパンジーに接種してクールー病と似た症状の病気をひきおこすことを証明しました。
こうして、それまで別々に報告されていたクロイツフェルド・ヤコブ病、クールー病、羊のスクレイピー病が一つの疾病としてつながったのです。現在はこれらの病気は「伝達性スポンジ状脳症」と一括されています。
つまり、それまで原因不明の変性疾患として三大初老期痴呆の一つとされていたクロイツフェルド・ヤコブ病は本体こそ未だ詳細不明ですが、何らかの病原体による、非常に長い潜伏期間をもった感染症であったのです。感染する認知症です。
感染症であることが判明してから振り返ってみると、クロイツフェルド・ヤコブ病の患者さんを一生懸命治療、看病した医療従事者が、20年以上後にクロイツフェルド・ヤコブ病になっていました。あまりにも潜伏期間が長いので、まさか若いときに感染したということに気付かなかったのです。さらにこの病気を持っていた方から採取した脳硬膜や角膜を移植された人が後にクロイツフェルド・ヤコブ病になるといった医原性のクロイツフェルド・ヤコブ病の存在も知られるようになりました。
それではクロイツフェルド・ヤコブ病はそれほど頻繁に発症しないのに、クールー病はなぜ集団発生するのかというと、クールー病にかかるフォレ族にはカニバリズム(食人儀式)という習俗があったのです。部族の中に死者が出ると、その人を悼んで皆で死体を食べる風習があったのです。そして脳は主に女性が食べていたために女性を中心に集団発症したというわけです。
さて今年の3月に吉野家が牛丼販売の時間帯を11時から24時までに拡大したことで、多くの人の関心から遠ざかった感がある狂牛病(BSE)問題ですが、医学的にはまだまだ決着がついているわけではありません。
狂牛病は正確には牛海綿状脳症(Bovine Spongiform Encephalopathy)と言います。この病気の歴史はそう古いものではありません。1985年、イギリスの牧場で奇妙な症状・経過を辿って乳牛が同時多発的に死亡したことに始まります。
本来おとなしいはずの乳牛が急に攻撃的になったり、歩行が困難になって死亡するという例がイギリスのあちこちで8頭もでてきたのです。1986年、この症状で死んだ牛の脳を電子顕微鏡検査で脳のあちこちがスポンジ状に空胞化して特殊なグリア細胞が増殖していることが分かりました。クロイツフェルド・ヤコブ病、クールー病、スクレイピー病とまったく同じ「伝達性スポンジ状脳症」の一型だったのです。
起源はスクレイピー病の羊にあると考えられています。本来草食動物である牛ですが、牛乳を効率よく産生して搾取するために、ヨーロッパでは仔牛は生まれるとすぐに母牛から引き離されて人工飼料で育てられます。その飼料が「肉骨粉」です。
肉骨粉とは羊、牛、豚の食用肉を取り除いた部分や死んだ家畜を加工して粉末にしたものです。もともとは草食であるはずの牛が無理矢理同種の動物の死体を共食いさせられているのです。この肉骨粉の材料の中にスクレイピー病で死んだ羊の死体も入れられていたのです。
この病原体は前にもお話したように通常の過熱や化学物質では死滅しません。このために仔牛の頃から肉骨粉を食べさせられていた牛が大きくなってスポンジ状脳症になったと考えられています。
一連の伝達性スポンジ状脳症をひきおこす病原体はその後の研究で、核酸をもたない異常型の蛋白質「異常プリオン」だとの説が有力ですが、未だ確定されたものではありません。遺伝情報を持たない蛋白質が感染して増殖するとなると、生物学の根幹をくつがえすことになります。蛋白質は生物とは考えられないからです。
プリオンが本当に犯人なのかどうかについて話をするとちょっとやそっとでは終りそうもありませんので、このテーマは後日に回させていただきますが、いまだに電子顕微鏡で本体の姿をとらえることはできませんし、抗体も確認されません。不気味な病原体です。
アメリカは国内の牧畜業界の要請を受けて日本の要求する全頭検査を拒否して、早期にアメリカ産牛の全面輸入再開するように圧力をかけてきています。潜伏期の長さを考えると、危険な輸入牛を食べたとしても病気が発症するのは10年以上先です。将来日本でスポンジ脳症が多発したとしても、その時「ごめんなさい」と言えば許されると思っているのでしょうか。
インド洋沖の給油をはじめ、政治、経済のあらゆる場面で、わが国はアメリカの属国であるという苦々しい現実を見せつけられていますが、食は国民の生命に直結した大問題です。この狂牛病に関連したアメリカ産牛の輸入問題だけは、けっして譲ることなく主権国家として毅然とした対応をつらぬいてもらいたいものです。


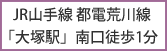


 クリニック西川
クリニック西川