EBM(Evidence-based Medicine)という医学の流れが1990年代からカナダを出発点として世界中に広まりました。日本語では「根拠に基づいた医療」と呼ばれます。
医療の分野に、より科学的な手法を取り入れようとする運動です。具体的には、治療法を選択する場合に、理論や経験や権威者の判断ではなく、確固とした疫学的証拠に基づいて、科学的に判断をすべきであるという考えが最大の特徴です。
それまでは、あくまで生理学的理論を大原則としてはいましたが、それに加えて実際に治療にあたる医師の経験や、その分野における権威者の意見などにしたがって判断されて治療法が選択されることが多かったのです。したがって、治療する医師や国によって治療法が違うことは少なくありませんでした。
もちろん、それまでの医療が当てずっぽうに行われていたわけではありません。実験的なデータや、臨床試験(実際に患者さんを対象とした実験的な治療)での成績などを基に、最良と考えられる治療法を選択してきました。
しかし、そういった選択基準だけでは、「×××は実験で、抗菌作用や抗酸化作用が示されたため健康に良い」といったふうに、実験室の試験管の中で認められただけの効果をもとに売り上げを伸ばす健康食品や、「芸能人の○○さんがこの方法で10kg痩せた」ということで流行するダイエット法とたいして変わりがない例もでてきます。
そこで、より厳格で正確な研究手法での実験結果(エビデンス)に基づいて治療法を選択しなければいけないという考えが広まっていったのです。我が国においてもこの考え方は多くの医師の賛同を得て、いまや「エビデンス」なしには何も語れない雰囲気になってきています。大変喜ばしいことです。私の所属する医師会のある先生などは、1回の演説(演説好きな方)の中に「エビデンス」ということばが5、6回でてきます。
ただ、私がとても心配なのは「エビデンスって本当にエビデンスなの?」という点です。というのは、現在「エビデンス」といっている根拠を生みだす主な研究方法が疫学的(統計的)手法だからです。 私は昔、数年の間、脳神経細胞に関する生理学的・薬理学的な基礎研究に携わっていました。基礎医学の研究においても、実験結果から得たデータを基にしてだした結論を客観的に、多くの人達に納得させるためには、統計学的な手法を欠かすことができません。このために、私はまる一年かけて統計学を学びなおしました。
当時は計算そのものを電卓による手計算でしなければならなかった時代でした。今は、エクセルなどを使って、データをパソコンに入力しさえすれば、通常用いるような検定ならば、簡単に計算してグラフまで作ってくれますから、一生懸命覚えた計算方法は今や無用の長物になってしまいました。
しかし、やたらと「エビデンス」がわがもの顔であふれかえる今になってくると、あの当時の勉強がむだではなかったと改めて実感します。なぜならば、計算そのものはパソコン任せでよいのですが、統計の意味するところを理解していなければ、ただただ数字やグラフに踊らされて、ごまかされてしまうからです。
残念なことに、一般の人に限らず、大学などで研究に携わっている人の中にも、統計学的に示された結果を誤解している人がいるのが現実です。「危険率5%で有意な差が認められた」と聞くだけで、その結果を神のご託宣のように信じきってしまう人が多いのです。
ここで統計学を十分に理解していない人が、間違った判断をしてしまう危険性を幾つかご紹介しましょう。
第1に知っていただきたいことは、ある事象について統計的な手法を使って他人を説得するということは、その事象が統計的な手法を使わないと説得できないほど不確かなことであるということを意味しているということです。逆説的でとってまわした言い方ですが、よく理解してください。
「サッカーボールはゴルフボールよりも大きい」ということを納得してもらうのに、統計学は必要でしょうか。誰が見ても一目瞭然な事実に対して統計的な処理はまったく必要ないのです。
「A社製のゴルフボールはB社製のゴルフボールに比べて雨の日にも回転数が影響されない」といったような、ごくわずかな差で、結論に不確かさが予想される場合に、相手を説得する手段として用いられるテクニックなのです。この不確かさの程度が危険率と呼ばれるパラメータです。
「5%の危険率でAとBに有意差が認められた。AのほうがBより重いといえる」という結果は、「AはBより重いと思う。この結論は95%の確立で信頼できる(信頼係数95%とも言う)が、5%の確立では間違っているかもしれません」と言っているのです。
2番目、これもしばしば見かける誤りですが、信頼係数の大小と、差の大小を混同しやすいことです。「Aという薬はBという薬より信頼係数99%で有意に効果があった。一方、AとCという薬との比較では、やはりAのほうに有意な効果が認められた。ただし、AとCの検定試験の信頼係数は95%だった。この報告を聞いたときに3つの薬の中でAという薬がいちばん優れた効果を示し、2番目に有効な薬はBで、Cは一番効果が弱いと勘違いしてしまう人がいるのです。
信頼係数(危険率)は比較している2つのグループ間の差の大きさを表しているわけではありません。出された結論に対する信頼性の高さを表しているだけです。3つのグループの差はそれぞれのグループの平均値を比較しなければいけません。
第3は、統計的な検定は相手を説得するための手段であって、それ自体が真実を語っているものではありません。かなり穿った言い方をすれば、自分の言いたい主張をより真実らしく見せかけるための手段だとも言えます。グラフもそうです。横軸や縦軸の刻み方は作成者の思うがままです。わずかな差を強調するために、横軸を圧縮して縦軸を引き伸ばしていらない部分を切り落とす手段はしばしば使われる方法です。
 |
地球温暖化の危機を訴えかけるためのグラフを作る場合に、横軸を年単位に目盛って、縦軸を0度から40度までのグラフで示すと、それを見た人はたいした危機感を感じません。しかし、横軸を10年単位の目盛りにして、縦軸を1980年の時の平均気温を0度として、縦軸は上方をプラス、下方をマイナスの0.5度単位の変化値で表しますと(気象庁発表の世界の年平均気温参照)、否が応でも地球が未曾有の危機に直面しているという印象を与えます。
 |
第4は、統計学を使って、真実に近い結論を出すための絶対条件は、統計計算をするための基礎となるデータが恣意的ではなく、公正に得られたものであるということです。つまり、基礎となるデータが何らかの意図を持って、公正さをかく手段で得られたものであったら、どんなに厳密な統計的手法を使ったとしても、真実とはかけ離れた結論が導き出されるということです。
第5に知っておかなければならないことは、統計計算はあくまでテクニックであるので、本来の使い方とは逆に使えば、自分が導き出したい結論に沿った研究方法をデザインすることもできるということです。統計学に精通している人の手にかかれば研究結果はかなりコントロールできるのです。
最後に「棄却検定」という奥の手もあります。棄却検定とは厳密に抽出したはずだったサンプルを対象に実験をしたはずが、結果の中に、あり得ないような数値が出てきてしまって、その数値があるために統計的な検定が成り立たなかったり、結果に信頼性が得られない事態におちいった場合に用いられます。
棄却検定にかけて、そのデータは「除外してもよろしい」という科学的なお墨付きをいただけば、堂々とそのデータを廃棄してかまわないのです。しかし、あくまで統計学的に廃棄してよろしいということであって、本当に廃棄するかしないかは研究者の判断に任されます。
こういう都合の悪い数値を除いてから、再度データを眺めてみると、まだ目障りな数値があることに気付いたとしましょう。そこで、再度棄却検定を行って、またその数値をとりのぞきます。これを繰り返していくと、とってもきれいにそろったデータができあがっていきます。
本来、EBMとは今まで行われてきた診療行為自体を、批判的な立場に立って見直すものなのです。厳密にEBMというためには次の5つの手順が必要です。(1)患者の問題の定式化、(2)定式化した問題を解決する情報の検索、(3)検索して得られた情報の批判的吟味、(4)批判的吟味をした情報の患者さんへ適用、(5)以上(1)から(4)までの手順の評価。
このうち最も重要なのは④の手順です。つまり、質の高い臨床研究によるエビデンスがあっても、ただ盲目的にそれに従って患者さんへの診療を行うのではなく、個々の患者さんの特性や価値観、またおかれた医療環境や医療チームの技術水準などを考慮して最終的な判断をしなければなりません。
しかしいつの間にか、まことしやかに数字やグラフを示せば、それだけで確かな「エビデンス」だと誤解する人が増えてきてしまったのです。
また、ある情報がエビデンスとして提示されても、将来的な研究で覆される可能性が常にあるということも忘れてはなりません。100件のエビデンスのうち23件が2年以内に覆され、そのうち7件は活字として発表された時点で既に覆されていたという調査もあります。 なぜ、こんなにしつこく「エビデンス」に対して懐疑的なことを書くのかというと、医学界が医療関連産業に取り込まれている危険を感じているからです。
一人で開業していると、ウィークデイに開催される大きな学会にはなかなか参加できません。参加できるのは土曜日の午後や日曜日に開かれる研究会です。そういう研究会はたいてい製薬会社がスポンサーとしてついています。
もちろんちゃんとした学術集会ですから、スポンサーの製薬会社の薬を宣伝する会ではありません。第一線の研究者がとても役に立つお話をしてくれます。しかし、このところメインの講演者(しばしば外国の有名な教授を招待する)のお話が、スポンサーの薬を推奨する内容であることが多いのです。
同じように「うつ病」をテーマにした研究会なのに、A社後援の研究会ではアメリカの有名な教授がA社の抗うつ薬がとても優れているという内容の話をする。次の週にB社後援の研究会に出席すると、今度はドイツの教授がB社の抗うつ薬がびっくりするほど優れているという話をするのです。
しかも、それぞれちゃんとした(?)研究結果をもとに、立派なエビデンスを示しているのです。私にはどうしてもそれぞれの製薬会社御用達の学者としか見えません。この傾向はここ数年急速にあからさまになってきています。
とはいっても、業界と御用達学者との癒着は今に始まったことではありません。以前はもっと露骨に、その分野の権威にとりいった製薬会社の薬が売れたのです。そういう背景がEBMを叫ぶ大きな動機でした。しかし、EBMの本当の意味を理解していなければ、いくら「エビデンス」という言葉を使っても、結局は昔と同じようにその分野の権威と製薬会社とのハネームーン関係は変わらないのじゃないでしょうか。いや、むしろエビデンスで理論武装しているだけ、なおさらやっかいかもしれません。
私がこのテーマを書くきっかけは、先ほど述べた研究会で、久しぶりに顔を合わせた現職の若手研究者が、その発表の胡散臭さを微塵も感じずに「○○先生は本当にすばらしい」と感嘆していた姿に唖然としたからです。
先週のコラムで書いたように、アメリカの医学界は製薬会社、保険会社から巨額の支援を得た医師、医学者が跳梁跋扈しています。日本の医学界はどうなんでしょう。研究にはお金がかかりますが、国からの研究助成金はとても少なくて、それだけではまともな研究はできません。スポンサーがあってはじめて成り立っているのが現状です。
しかし、スポンサーはスポンサーとして、自然科学者は真実の究明という本来の目的に向けて邁進してほしいものですが、製薬会社の競争論理の前にはなかなか難しいのが現状ではないでしょうか。それゆえに情報を受けとる私たちも「エビデンス」と称するものに対して、しっかりと批判的な目をもって、その奥に隠されているものを見極めなければならないでしょう。


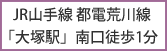


 クリニック西川
クリニック西川